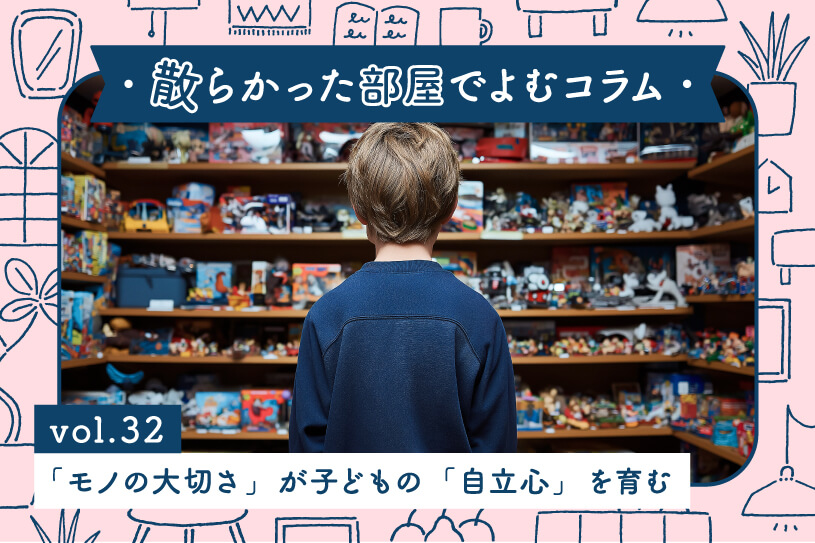
買い与えすぎ注意!「モノの大切さ」が子どもの「自立心」を育む|カネノミホの散らかった部屋でよむコラム #32
掃除はめんどくさい!家事もズボラな元片付け苦手人間という整理収納アドバイザーのカネノミホが、毎日をラクに過ごす片付けのヒントを教えます。
お金の使い方にはまあまあうるさい、整理収納アドバイザーのカネノミホです。
「これ欲しい!」「今流行ってる!」とねだられると、ついつい財布のひもが緩んでしまう…
卒業、入学(進級)、誕生日、クリスマスと祖父母から送られるプレゼント…
気づけば家にはおもちゃやゲーム、洋服がいっぱい。そして、子ども達がそれらを大切にしているかというと…意外とそうでもない。「遊ばないの?」と聞くと、「もういらない」とあっさり。ばっさり!?
実はこれ、怖いことなんです!!
モノが簡単に手に入る環境が当たり前だと、子どもは「モノの価値」や「大切にする心」を学ばずに成長し、将来の「自立」に悪影響になることも。
今回は、モノを大事にする子に育てる方法についてです。まず、買い与えすぎのデメリットを考えてみましょう。
1. 「簡単に手に入れる」と価値を感じない
私たち大人も、苦労して手に入れたものほど大事にしませんか?例えば、コツコツ貯金して買った車はピカピカに磨くのに、職場で支給される備品はすぐどこかへいっちゃうけど「ま、いっか…」なんてこと、ありませんか?
子どもも同じ。「欲しい!」と言えばすぐに手に入る環境だと、「モノのありがたみ」がわからなくなり、結果として大切にしない・使わない・次々欲しがるの無限ループに。
私は小学校での講師経験もありますが、鉛筆や消しゴムを失くしても、「また買ってもらえばいいや」という子は、大事に扱うことを学びません。そして「失くしても平気」「壊れても困らない」と、みんなで使うモノも大事にしなかったり、何にも執着しなくなったり、モノの価値を感じなくなります。
2. 「欲しいものはすぐ手に入る」と自立心が育たない
買い与えすぎの問題は、「努力しなくても手に入るだろう」という誤った価値観を植え付けてしまうことも。例えば、勉強やお手伝いを頑張らなくても、何でもすぐ買ってもらえると、「欲しいモノは、頑張らなくても手に入る」と思い込むようになります。
そして成長すると…
✔︎ 欲しいモノは、すぐにクレジットカードやリボ払いに
(でも支払いは考えない)
✔︎ お金を稼ぐ苦労を知らずに、欲望だけが膨らむ
(お金を貯められない)
✔︎ お金の管理ができない
(計画性を持てない)
一人暮らしを始めたり、就職してからと苦労するのは子ども自身です。では、どうしたらいいか?
答えはシンプル。欲しいモノが「本当に必要か」「どう手に入れるか」を考えさせることです。
例えば…
✔︎ お小遣いの中でやりくりさせる
→ 欲しいものの優先順位を考える練習
✔︎ お手伝いをしたら報酬を渡す
→ 労働と対価の関係を学ぶ
✔︎ 「本当に今、必要か?」と問いかける
→ 衝動買いを防ぐ習慣
「簡単に買わない、与えない」ことが、子どもにとっては良い勉強。「買う前の工夫」は子どもの成長の鍵です。
また、3RやSDGsを学んでいる小学校高学年以上なら、リユースの活用もおすすめ。うちの子は「新しい野球のバットが欲しいなら、今のバットを売ったらとなんとか買えるかも」と考えて、自分で調べていたりしましたよ。
そして、「買い方」を教えるのも親の役目です。子どもに「選び方」「買い方」を教えながら、一緒に買い物をする機会に
✔︎ 長く使うなら安いものより、少し高くても長く使えるものを選ぶ
✔︎ 安い(セール)からと、無駄なものは買わない
✔︎ 今欲しいけど、一晩考えてから決める
こんな大人の姿を見せるだけでも、お金やモノの価値観を学ぶ機会になります。
○ モノを大切にする習慣がつくと
→お金の管理もできるように
○ 買う前に考える力がつくと
→無駄遣いせず貯金ができるように
○ モノやお金の管理が上手になると
→時間管理もできるように
となり、いいこと尽くし!買い与えすぎは、お金やモノを大事にできない大人をつくります。
「モノの大切さ」を学ばせることが、子どもの自活力が上げる、未来の自立につながる一番の投資かもしれませんよ!
○お知らせ
定期的に開催中の「整理収納アドバイザー2級認定講座」。1日で資格も取得できる人気No.1講座を受けてみたいという方は、ぜひチャレンジを!
2025年5月11日(日)10時10分〜17時
詳細・お申込みはこちら